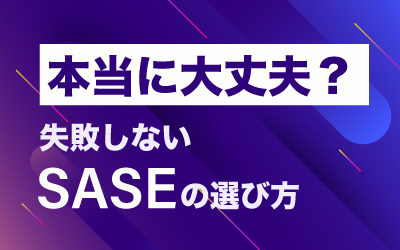最新のインサイトセミナー
稼働停止リスク?取引先のガイドライン準拠状況?
サプライチェーンと制御システムを保護する
製造業の2大サイバーリスク戦略
ガイドラインには載っていない。
現場目線で実効性の高い工場セキュリティの進め方
詳しくはこちら
SERVICE
- SASE
- セキュリティ
- WAN/LAN
- プラットフォーム
- IoT
-

Global SASE
with IIJ Omnibusグローバル企業のデジタル変革を支えるマネージドSASEプラットフォームです。
詳しくはこちら
-

マネージドXDR
ソリューションエンドポイントからプラットフォームに及ぶ企業全体のセキュリティ運用を統合、生産性を高めて検出と対応を強化します。
詳しくはこちら
-

ICT運用リエンジニアリングソリューション
高度化・複雑化するセキュリティアーキテクチャとUXの向上を目指し、DXに向けたICT運用トランスフォーメーションを実現します。
詳しくはこちら
統合運用管理サービス DataSnow
ネットワーク機器・オンプレミスのサーバから IaaS/SaaS そして SASE まで一元管理することで、IT インフラ運用におけるお客様の負担軽減と運用品質向上を実現します。

マルチクラウドインターコネクト(Megaport)
オンプレミスからクラウド、クラウドからクラウド、拠点からクラウドへのあらゆる接続を統合し、ネットワークパフォーマンスとコストを最適化する次世代クラウド接続ゲートウェイです。

IIJセキュアLANソリューション with IIJ Omnibus
セキュアでシンプルなLAN環境を実現する、法人向けクラウド型LANソリューションです。無線アクセスポイント、L2/L3スイッチのエッジデバイスをSDNでネットワーク制御します。

マネージドWANサービス SmartWAN
業務や用途に応じた最適なネットワークを、設計・構築・運用までワンストップで提供するマネージドWANサービスです。

国際インターネットVPNサービス Net de! World
インターネット上で、セキュアに海外お客様拠点との通信を提供するサービスです。現地アクセス回線の手配、VPN機器の提供と設置、保守をパッケージにしてご提供します。

海外拠点ネットワーク調査ソリューション
海外拠点を抱えるお客様向けに現地のIT環境を調査し、海外駐在員事務所・現地法人のIT環境・セキュリティ問題を解決します。

海外拠点開設支援
海外現地オフィスの新規拠点開設サポートからITインフラの構築・運用までをワンストップでご提供します。

ネットワークアウトソーシングサービス
コンサルティングから、設計・導入構築・運用管理に至るまで、トータルにネットワークのアウトソーシングを可能にするサービスです。

グローバルネットワークアウトソーシングサービス Global NOS
国際ネットワークの通信事業者の選定・契約から導入・運用までをワンストップでご提供します。

-

ビジネスコラボレーションソリューション Webex
安全性と高い信頼性でつながり、コミュニケーションし、コラボレーションするための統合プラットフォームです。
詳しくはこちら
-

IoTトラストサービス™
なりすましデバイスによる不正データ送受信の脅威から守り、認証されたIoTデバイスとIoTデータ収集基盤の間で安全なデータ送受信ができる環境をご提供します。
詳しくはこちら